
©Jリーグ
サッカーの競技規則は毎年細かく修正されている
ときとして同じ事象でも1年前とは違った判定になることがあり
見ているほうが規則改正を知らなければ
審判がミスをしたと思われることになる
どうしてこんな事態になっているのか
アジアサッカー連盟に9年間出向して審判部長を務め
世界的な競技規則改正の事情をよく知る
日本サッカー協会審判委員会の小川佳実副委員長に聞いた
2019年のマリノス対レッズの騒動は「大切な判断だった」
ヨーロッパには自分のサッカー観やプレーに対する考え方がすごく強い審判が多いですね。そして国によっては手に当たればすぐにハンドという反則を取るという傾向もあったりします。競技規則があったとしても、みんなピタッと判定が同じにはならないんですよ。でも、ある一定の範囲の中で同じになるようにして、その範囲を超えちゃいけないとは思います。
「手に当たったらなんでもハンド」というのは、やっぱり範囲を超えてるんです。そういう範囲から出ていることについては競技規則を決定している国際サッカー評議会(IFAB)も指導しています。たとえばプレミアリーグではオンフィールドレビュー(ピッチ横のビデオモニターでの確認)を審判がしない傾向があったので、今年の規則改正で、オンフィールドレビューをすべき時にはしなさいと書いてあるんです。
大切なのは、すべてが一緒ということではなくてその範囲から外れてはいけないということです。そしてその範囲に収まる判定基準でプレーしておかなければ、国内の大会ではよくても国際サッカー連盟(FIFA)の大会に出たときには通用しなくなります。
そしてビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が導入されることになったから、細かいところまで規則で述べなければいけなくなったのだろうと思いますね。PKのとき、キッカー以外がペナルティエリアに入ったらいけないのですが、体が入っていても地面に接している足がラインの外だったら大丈夫と明確になりました。普通は複数の人の地面に接している足まで見ていないでしょう。VARがあるからこそできる判定です。
ハンドも、どこから「腕」かということが今年細かく規定されました。でもそこで規定してある「脇の一番奥から水平に線を引いたところ」が境目と言われても、どうラインを引くかで変わってきますよね。それでも少しでも理解の幅を狭めるために定義されてるんです。今までは自分の考えで審判が取っていたのですが、これで一定の範囲の中に収まるのではないかと思います。
そうやってVARが介入することによって審判の持つ権威が削られるという意見もあります。でもサッカーの判定はもう「オレが決めたのだから従え」という世界ではなくなってきました。ただ、その中で審判の判定はリスペクトされるべきだし、時として間違うこともありますが、審判は競技規則の範囲内で与えられた権威・裁量の中で最大限の能力を発揮することが求められているんです。
権威のベースは基本的にやるべきことをきちんとやってることなんですよ。ピッチに立っている人たちにそういう共通の理解があって、その上で審判に任せますということになってこそ、審判に権威があるんです。
審判は元々両チームの意見が分かれたとき、仲裁役になってもらうために呼ばれた立場の人だったんです。そういう歴史的な部分を監督や選手は理解してほしいと思います。そして審判は、もしかしたら1試合の判定でレフェリング・キャリアが終わってしまうかもしれない。そういう覚悟で臨まなければいけないということだと思うんですけどね。
2019年7月13日の横浜F・マリノス対浦和レッズの試合、後半14分にゴールが入ったかどうか判定が下るまでに非常に時間がかかったという場面がありました。結局、松尾一主審は自分たちの目で見た判定に戻しました。あれは大切な判断だったんです。混乱させたけど、ちゃんとルールの範囲である元に戻したのがよかったと思います。

ルール改正で1年前とは逆の判断になることもある
競技規則の改正は毎年行われています。その中には混乱させる恐れがあるものもあります。たとえば2019年ルール改正のメディア向け説明会で使ったビデオは、2020年に解釈が逆になりました。だからあえて今年のルール改正の説明にも使ったんですよ。それはこの場面です。
相手選手が蹴ったボールが偶然手に当たり、そこからドリブルして得点が生まれています。2019年、この場面はゴールにはならないと説明しました。それは意図的ではないにせよ手に当たり、それが得点に結びついたからです。今年のルール改正で、得点を認めないのは手に当たった「直後に」という言葉が加えられたため、この場面では手に当たったことは確かですが「直後に」ではないということで、ゴールが認められることになりました。
私たちとしては、自分たちの説明が1年経ったら逆の判断になるわけです。同じビデオを使うとそれがハッキリするので、そういう表現を避けたいと思う人もいたかもしれません。ですが、世界的にも同じような理解だったので隠すことなく、一番分かりやすいと思ってそのビデオを使用しました。
こういう競技規則の改正について近年、大きな出来事が2つありました。1つは1997年、ルールを簡易な表現にするように変わったんです。もう1つは2016年の改正です。これはサッカーのルールが制定されて130年の歴史の中で最も大きな改正と言われるものでした。
実は1997年は私が日本サッカー協会(JFA)に入った年です。そのとき審判委員会の浅見俊雄委員長を中心に私もお手伝いさせてもらいながら、かなりのボリュームの言葉を平易にする作業をしました。そして次の2016年は、私が出向していたアジアサッカー連盟(AFC)からJFAに戻ってきた年なんです。そこで2回目の大変な作業でしたが貴重な経験をさせてもらいました。
2016年は多くの項目で改正が行われました。三重罰と言われる、ペナルティエリア内での反則は「PK」「退場」「次節出場停止」になっていた点が改正されたのもこのときです。そこで多くの改正があったため、逆に明確ではなかった部分も浮き彫りになり、それを定義しているというのが今の状況です。IFABでテクニカルダイレクターを務めるデイビッド・エラリー氏は、今年で改正は一応収まるのではないかと言っていました。
また2016年の改正の翌年、IFABは将来的な戦略というのも発表しています。そこでは2017年から2022年の間に競技規則をサッカーの発展に向けてどのような観点からよりよいものにするかということが書いてあります。公平性、高潔性、普遍性、多様性などについて触れてあり、さらに「テクノロジー」という言葉が入って、VARにも触れてありました。
そういう意味でも2016年のルール改正に抜本的な部分があり、それに基づいて「サッカーが求めるものは何か」ということ、競技規則を通じてサッカーのイメージを向上させるということ、サッカーの競技の利益になるよう提案されたものはテストを経て取り入れていくこと、などが変わってきたという状況です。
元々IFABは保守的で大幅な改正に毎年取り組むような組織ではなかったのですが、サッカーの映像が世界中に配信されてビジネスの1つになり、プロフェッショナルのサッカーに求められるもの、たとえば得点が見たいとか、汚いファウルには断固たる措置が執られてほしいとか、そういうのが出てきたことで組織の考え方も変わってきたのだと思います。
それに、これは審判の世界の中にいて感じていたのですが、審判はどちらかというと審判員の考え方に基づいてルールを解釈していました。それを、競技規則の精神のもとにサッカーが期待する判定、またサッカーを発展させていくために必要なことは、ということをしっかり理解して適用していく、そしてその中で経験を生かしてマネジメントしていくというように変わってきました。
こういう状況を、選手、チームの指導者、そして見ている方々が知らなければ、「この前まではよかったのになぜ?」と言われて、最終的に審判が大変な思いをしてしまいます。これだけ毎年改正があるということをみなさんに伝えていくというのは本当に大切だと思っています。
私が審判委員会の委員長になったとき、それまでは年2回程度であったメディアの方々への説明会を、1ヶ月から1ヶ月半の間に1回、その間に起きたレフェリングについて説明会を開催することにしました。最初は担当する審判指導者の方々も含めて大変でした。報道も「あの判定は誤審だった」という内容が先行しましたから。
審判員を守れという意見も寄せられました。もちろん私も守るというのは大前提なのですが、ルールへの理解を深めないと逆に審判が言われっぱなしになると思ったのです。何か起きたときだけ記者会見を開いても、メデイアの人も受け入れてくれるはずがない。だからよかった判定も問題があったジャッジも含めて伝えて理解してもらおうと思いました。
そして映像を使って説明することで、最初は審判と同じ理解ではなかったものを合わせていく。そのためにはミスも伝えていくということをやっていました。今は審判員の方々もみんな理解してくれたと思います。
レフェリーはどっちにも文句を言われる可能性がある立場
IFABの中にテクニカル小委員会というのがあります。IFABから委ねられたルールの原案を作るところなのですが、その下に2つの組織があります。1つはテクニカル・アドバイザリー・パネル(TAP)と言って審判の技術を担当する組織、もう1つはプロフェッショナル・アドバイザリー・パネル(PAP)と言って、元選手や監督で構成されている組織です。その第1回の会合が2014年10月、北アイルランドのベルファストで開催され、私はAFCの審判部長だったのでアジアを代表して参加しました。ちなみにPAPにはアジアを代表して中田英寿さんが参加していました。
それまで競技規則というのは審判のテクニカルな人間だけが考えていたのですが、元選手や監督さんの話を聞いて、両方の側面からどうしていくか考えることになったんです。この話し合いは今も続いていて、私は2015年にロンドンで開催されたときにも参加させてもらいました。
2014年に参加したとき、初めてVARの話が出ました。2018年ロシアワールドカップでは採用することになったのですが、2014年の時点ではまだ反対意見もありました。当時はヨーロッパサッカー連盟(UEFA)の審判委員長で、現在はFIFA審判委員長のピエルルイジ・コッリーナさんも「1kmも離れた部屋の中にいる人間がどうやって判断するんだ」という意見でしたね。
でもそういう考えを打ち崩して、プロサッカーに求められるものは何かを革新的に考えるようになったんです。それまで保守的だった競技規則に対する考え方が、規則の精神はきちんと守りながら、どうやってよりよいものにしていくかというアプローチに変わったんですよ。そういう改革を行ったIFABダイレクターのエラリーさんはすごいと思いますね。
ただ、こうやって競技規則が変わっていくこと「なんでこんなに変わるんだ」と感じる人が多いだろうとも思います。混乱させるだけじゃないかと。
たとえば普通はドグソ(DOGSO : Denial Of an Obvious Goal Scoring Oppotunity/決定的得点機会の阻止)の状態でファウルがあったときは退場になります。ですが去年、ファウルはあったものの主審がアドバンテージを適用したり素早いFKを認めたときは、ファウルそのものが悪質でなければ、退場ではなくて警告ということになりました。
そして今年、同じような場面で警告に該当するようなファウルがあったとしたら、警告はなくなるということになったのです。実は去年の時点で、退場に相当するファウルが警告になるのだから、警告に該当するファウルはどうするかという問題が発生すると気付いていなかったんですよ。
「赤」が「黄」になるのだから、「黄」が「なし」になるというのは理屈が通っているのですが、その整合性を加えたのが今年になったんです。他にもそうやって整合性を取っていて、そのほうがみんな納得しやすいと思います。でもこういう部分は相当細かく説明しても難しいところです。
また実際の主審にとっても難しいところがあります。たとえばGKがペナルティエリアの外に飛び出してイエローカードに相当するファウルで止めた、ところがボールはコロコロとゴール方向に転がっていて、攻撃側の選手が誰か触ればゴールになる。もしそこで主審が笛を吹いてFKとすることは、それはサッカーが求めていることではありません。
さらに言えば、ペナルティエリアの中でトリッピング(反則行為のひとつ)があり、でも攻撃側の選手が簡単にゴールできるところにボールが転がったら、それはPKではなくてアドバンテージを取ってゴールに入るかどうかを見るという判断が求められます。
ところが、FKやPKを取らなかった場合、結果としてゴールが決まらなければすごく非難もされると思います。逆に、誰もがゴールを期待していた状況で笛を吹いてしまったら、それも批判されますよね。結局レフェリーはどっちにも文句を言われる可能性がある立場なんです。しかもルールが改正され、それに従ってレフェリーが笛を吹いたときに「今までと違う」という、改正を知らないことから非難されることもあると思うんです。
先日、あるチームのGMから今回の規則改正についての質問が来ました。攻撃しているときにこの改正はどうなのかという話になったので、私は「自分たちが攻めている立場だけではなく、守備側だったら、また守っている立場だけではなく、攻撃側だったらということで選手に話をしてください」と伝えました。両方の立場から考えると納得しやすいんですよ。そのGMは「選手にストレスがないようにするために理解したい」とおっしゃってました。素晴らしいと思いますね。
競技規則は審判のものではなくて、サッカーに関わるすべての人たちのものなんです。だから選手や監督さんの目線を入れた上でよりよいものに競技規則はなっているのではないかと思います。だからこそ私たち審判というのは、競技規則を審判だけではなく多くの人に広めていくということがすごく大切になってくるのです。

©Jリーグ
「中東の笛」という表現はとても残念
私は1994年のヤマザキナビスコカップ決勝の主審でした。神戸で開催されたヴェルディ川崎vsジュビロ磐田ですね。あのときは、ラモス瑠偉さんはじめ結構面白い選手がたくさんいらっしゃいました。私は静岡出身で当時は教員でした。ジュビロには静岡出身者がたくさんいましたし、カズと三浦泰年の両選手は静岡学園のときのたった1年間だけでしたが教師と生徒という関係で教え子だったんですよ。
1997年3月に教員を辞めて4月からJFAの職員になりました。当時は不況で公務員志望者が増えているような時代だったんですけど、川淵三郎キャプテンや浅見委員長に席を用意していただいて、こんな機会はないと思って飛び込んだんです。まだワールドカップへの出場も決まっていないときでしたから、みんなには仕事を辞めることについて心配されました。
私が入ってJFAに審判部ができたんですが、当時の審判部って2人しかいなかったんですよ。それまでは東京FAの副会長で専務理事の植田昌利さん(JFA常務理事)が審判委員会の幹事として委員会の事務局を担当してくれており、JFA登録部職員がサポートをしていたという状態でした。そのような状況でしたから、当時はJリーグへの審判関係のことはJリーグで対応していたのですが、JFAに審判部ができたことで、今となっては当たり前になっているJリーグの審判関係の対応についてもJFAが対応することになりました。
私は現役審判員として笛を吹かなければならなかったので、もちろん割り当てには触れないという立場でしたが、JFA事務局として審判関係全体をとりまとめなければいけない、審判部部長代理という役職に就いていたので、非常に難しい状況だったことを覚えています。その当時は子供の教育のこともあったので静岡から引っ越す決断ができずに、東京まで新幹線通勤していたのですが肉体的にも精神的にも無理が来て、結果として審判を続けることが難しくなってしまい現役から引退したんです。
現役引退後、2002年ワールドカップに関わる業務を経て、改めて審判部部長として審判部での業務に携わる機会を頂きました。その後、プロ審判員の立ち上げにも携わり、岡田正義さん、上川徹さんなど当時は「スペシャル・レフェリー」と呼んでいたプロフェッショナル・レフェリーの制度を構築し、Jリーグで審判員として活躍されていたレスリー・モットラムさんに初のプロ審判指導者になっていただきました。それから審判の登録をアナログからWeb登録化にも関わることができ、審判のプロ化とともに、自分が審判をやっていた経験が、このようなから審判関係の新たな制度化に僅かではあったにしろ活かすことができたことは私にとっても貴重な経験をさせてもらいました。
そうしていると2006年7月、川淵キャプテンから呼ばれて「AFCへの出向の話があるが」と言われたんです。「いつからですか?」と聞いたら「9月から」って、もう2ヶ月しかない中で準備して。行ったらいい経験はさせてもらったんですけどね。
最初は2年の契約だったんですけど、AFCから延長のオファーがありJFAも認めてくれたので結局9年になりましたね。そういう意味ではサッカー界で審判の仕事はそんなに多くないのに、そこまで経験させてもらったのは、今考えると良かったなと思います。出向当初は辛かったですけどね(笑)。
AFCに行った最初の半年間ぐらいは「どうなるんだろう?」と思ってましたよ。英語力も不十分だし、モハメド・ビン・ハマム会長からも何かあるごとにエライ怒られたりとか。組織もきちんとしてなかったですね。それにアジア各国で判定基準の違いが目立ちました。
中東、東アジア、中央アジアでは、国民性、宗教、考え方が違いますからね。ワールドカップに出場しているUAEの審判に大会期間中に自宅へ招待してもらったことがありましたが、庭がサッカーのフィールド半分、そして家族5人に対して雇い人が30人いたことにびっくりしたこともあります。一方であまり裕福でない国の主審は月給30〜50ドルで働いているという話もありました。当時のAFCの2011年カタールアジアカップの時の審判の日当は100ドルで、1試合担当すると400ドルもらえるんです。中東の国のような豊かで恵まれているような国の審判にとってはさほどの金額ではありませんが、経済的に厳しい国の審判にとって400ドルは大金となるわけですよ。
ですからアジア各国の審判員を「アジアの審判員」として同じ考えを持って取り組むことが必要という話をしても、環境に大きな違いがあることから、話をすることだけで理解してもらうことは難しかったです。そこで私が考えたことは、審判員がセミナーに参加している期間中に「規律」の大切さを伝えようということでした。フィールドでのトレーニングでは、多くの審判員は自分が飲み終えたペットボトルをそのまま投げ捨てる中、私は、その捨てられたペットボトルを拾って片付けるようにしました。
そうすると、日本の審判をはじめ、何名かの審判員は当初から投げ捨てることはしないため、この状況は良くないということに気付いてくれるわけです。このような審判は、私が拾っていると自ら拾い始めてくれるようになりました。2006年からAFCに加盟したオーストラリアの審判も、自分たちはアジアとは違うという雰囲気を醸し出していた感じもありましたが、拾ってくれるようになり、それで中東の人たちも拾うようになりました。そしてだんだんみんな分かってきて、次第にちゃんと決められたところにボトルを捨てるようになったんです。
トレーニング会場に到着後、バスから降りる時も自分たちが飲む水を運ばない人が多くて、スタッフの女性がボールと一緒に運んだりしてたんですけど、意識が変わってきて自分で自分のものは運ぶようになりました。もちろん自分はちゃんとやっているというのを見せたいという気持ちもあったのも確かだと思います。
そしてこういうことをしっかりやるようになると、みんな規律を守るようになりました。試合の前に体を作って集合するようになったし、食事やトレーニングで自分を律するようになりましたね。そうやって自分を律することができないと、ピッチをマネージメントできないですよ。
もちろん私は厳しかったと思います。当時AFC審判委員長の国の審判を、規律を守らないことを繰り返したとということでAFCエリートレフェリーのリストから外すことを審判委員会に提案したりもしましたから。反対に規律、そしてテクニカル面がよければより高いレベルの試合を担当する機会を増やしたので、テクニカルがいい、きちんと体調をキープしている審判が増えたと思います。そうしたらいろんな国の代表チームの人から審判がよくなったと言ってもらうようになりました。うれしかったですね。そしてその声はちゃんと審判にフィードバックしました。もちろん、判定が正しくなかったことで、批判も受けることはありましたが。
そんなことを続けて審判の質は向上したと思うのですが、たまたまミスしたのを「中東の笛」と表現されたりするとすごく残念ですね。それに日本では「中東の笛」と言いますが、他の地域からは「東アジアの笛」と揶揄されることもあります。
もし判定が賄賂などによって左右されていたら、すべての試合を監視しているシステムがあるので、そこから間違いなくアラートが上がってきます。アラートが上がったということで調査が行われ、ある国でその対象となった審判員について私も参考人として呼ばれたこともあります。その審判員は3ヶ月ぐらい留置されていました。それくらい厳しくチェックされているんですよ。
帰国してJFA審判委員会の委員長を今年3月までの4年間務めました。今の審判委員会は、Jリーグを担当する部署、女子審判員を担当する部署、そして私が担当している国内審判ディベロップメントという部署です。私は審判委員会の副委員長としてこの部署の統括を担当し、指導者養成と地域の審判員の育成・強化、それからフットサルとビーチサッカーの審判員の育成・強化、そして競技規則や審判員の登録を取りまとめながら、合わせて国際関係のIFAB、AFC、アジア各国との交流など海外関係のレフェリーマターを担当する役割に就いています。
サッカーではすべての試合で両チームとも勝ちたい、得点したい、失点したくないという気持ちがぶつかり合っています。それを裁くという立場は、たぶん両方から100パーセント納得されることなんてないんですよね。そういう難しい立場であるというのを理解してもらいたいと思うし、そういう難しい立場でやる価値というものも審判は見出してるんです。
それはグラスルーツでやってる方も同じです。そういう人たちの気持ちというのを萎えさせないように周りの人たちが、そのときは感情的に言ってしまうかもしれないけど、あとでコミュニケーションを取ってほしいですね。
イングランドでは試合が終わった後、アウェイチームとファンサポーターがクラブのちょっとお茶を飲む場に集まって、そこに審判員も加わって話をするというのがあるんですよ。そういうのが文化になっていく一つの要因なのかなと思います。日本ではまだ難しいことかと思います。しかしながら、日本でも試合終了後、様々な立場で試合に関わった人たちが審判員といろいろな観点から話をする機会ができるようになったら、サッカーが文化になったと言えるようになるんじゃないかなとも思うんです。
Jリーグでも試合が終わった後に「ありがとう」と声をかけてくれる監督さんもたくさんいらっしゃるんですよ。そういう終わった後の対応は、日本の指導者の方々や選手の人たちにさらに広まってほしいと思いますね。
審判員との食事は立場上、避けていた
僕は東京と言っても、町田で横浜寄りのところに住んでるんですよ。オススメするとしたら、うちの近くのところですね。
僕は蕎麦が大好きで、海外から帰ってきたときにも必ず行っていた店があります。「つきみ野駅」の近くの「ほりのうち」という蕎麦屋さんですね。ここの「天麩羅せいろ」には松・竹・梅というランクがあるんですが、この一番下の梅ばっかり頼んでます。
あとは蕎麦がちゃんと食べたかったから3人前ほどのせいろで「へぎそば」というのを頼んで、これに天ぷらを頼んで女房と2人で食べるんですけど、量が多過ぎるくらいですよ。
僕は、今まで審判員と一緒に食事したりすることはほとんどありませんでした。立場的にそこは一線を引いてました。AFCに行っていたときも日本人と食事することはなかったですね。「日本人だけがいい思いをしている」と誤解されるんじゃないかと思いましたから。だから特定の審判員の誰かと食事というのは自ら避けていました。できなかったんですよ。それは今も一緒ですが、本音は審判の皆と楽しい食事をしたいことは確かですね。
紹介したお店
小川佳実 プロフィール

審判員として活動後、1997年に日本サッカー協会入りし、98年に審判を引退。2006年からAFCに出向し2015年に帰国。JFA審判委員長を4年間務めた。1959年生まれ、静岡県出身。
取材・文:森雅史(もり・まさふみ)

佐賀県有田町生まれ、久留米大学附設高校、上智大学出身。多くのサッカー誌編集に関わり、2009年本格的に独立。日本代表の取材で海外に毎年飛んでおり、2011年にはフリーランスのジャーナリストとしては1人だけ朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の日本戦取材を許された。Jリーグ公認の登録フリーランス記者、日本蹴球合同会社代表。
【関連リンク】
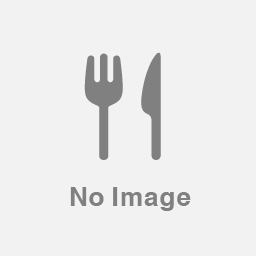













































































 「
「
 「
「 「
「





























 海辺の町でロックンロールを叫ぶ不惑の会社員です。90年代末からWeb日記で恥を綴り続けて15年、現在の主戦場ははてなブログ。内容はナッシング、更新はおっさんの不整脈並みに不定期。でも、それがロックってもんだろう?昨年本も出版しました。ピース!
海辺の町でロックンロールを叫ぶ不惑の会社員です。90年代末からWeb日記で恥を綴り続けて15年、現在の主戦場ははてなブログ。内容はナッシング、更新はおっさんの不整脈並みに不定期。でも、それがロックってもんだろう?昨年本も出版しました。ピース!












































































































































































































































 お客さんと会えない時間はやっぱり寂しかったですよ。元々、「お店を通して、多くの人に魚食文化を伝えたい」という思いではじめたお店でしたから。
お客さんと会えない時間はやっぱり寂しかったですよ。元々、「お店を通して、多くの人に魚食文化を伝えたい」という思いではじめたお店でしたから。






























































