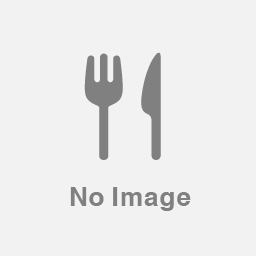夜中に帰宅すると、テーブルの上に、白い大判の冊子が置いてある。
『赤瀬川原平 カメライラスト原画コレクション』。
ボクの先生だった赤瀬川原平さんのカメライラストの画集だ。
ボクはカバンをおろして、立ったまま画集をめくった。
すごい。すごい。
ボクは画集を閉じた。少し飲んでいるから、先生に失礼な気がして、明日ゆっくり見ることにして、忘れないようにカバンに入れた。
翌日仕事場に来て、ちゃんと椅子に座って、机の上で画集を開く。
絵は、赤瀬川さんが80年台中頃から、いろんなカメラ雑誌にエッセイとともに掲載していたものだ。
ボクはカメラの趣味はないから、カメラ雑誌は読まない。
でもこのイラストを見るために、連載当時いつも書店で立ち読みしていた。そして、その面白いほどの緻密さに、いつもため息をついていた。
すべて鉛筆だけで描かれているが、カメラの質感表現が神がかっている。
赤瀬川さんは当時中古カメラウイルスに冒されていたから(自分で言っていた)、あらゆる中古カメラに興味があった。その方面の著作も多い。のめり込むように、クラシックカメラを見ていた。
そののめり込みが、笑っちゃうくらい絵に現れている。

まず、金属の表面の質感表現がすばらしい。
銀色の部分の、触り心地のすべすべした硬質感。
そこに刻印された文字の、微妙な凹み。
つや消し銀色の鈍い光と、黒く塗られた金属の重い反射。
角の微妙な丸みと、巻き上げネジなどのエッジの鋭さ。
金ならではの重量感。
そこだけ質感が全然違うレンズの、みずみずしいまでの透明感。
そして何と言っても、握るところの皮しぼの凸凹。これが特にすごい。どうやって描いたのかわからない。
ランダムのようで機種によって規則性があり、でも幾何学的ではない、細かいグニュグニュの模様が、細かいまま立体的に描かれている。
たしかにこう見える、見えるけど、人間の手でこんなに見たままに描けるものなのか。不思議ですらある。
赤瀬川さんの細密画は、下書きに写真をトレス(写してなぞる)していない。
現物を机に置いて、直に目で見て描いているのがわかる。
ほとんどのスーパーリアリズム絵画は元の写真があり、下書きやフォルムくらいは、そこから起こしてアタリを取っている。これはダヴィンチの時代から続いている。もちろん当時はまだ写真は無いが、その前身のカメラオブスキュラ、ピンホールカメラ的な器具を用いての、現実模写はあった。
それが絵描きとして「ズル」だという気持ちがあったのだろう。そういうことをしているのは、長いこと隠されていた。
今はそんなことより、堂々と写真を用いて、スーパーリアリズムの絵画が描かれている。
マンガでも、パソコンで写真を加工して、そのまま背景に使っているマンガ家も多い。
どういう手法を使おうと、でき上がった絵が人の心を打てば、それでいい。完成した絵が全てだ。
でも「写真を写して描くとズル」という人間の気持ちもわかる。面白い。
そういう意味で、赤瀬川さんの絵にはズルがない。
目で見て手で描いた特有のわずかな歪みが、全体を支配している。
そしてそここそが、赤瀬川さんのカメラ絵の、最高のおいしさになっている。
カメラという無機物に、命が吹き込まれて、どこか生き物めいている。
赤瀬川さんとカメラが、赤瀬川さんの目と指と鉛筆を通じて交わり、ひとつになって生まれたのが、この絵なのだろう。
だから、すごいだけでなく、うまいだけでなく、やさしい。
そして赤瀬川さんが生まれつき持つ、独自の静かなユーモアが、絵にも現れている。
古今東西、スーパーリアリズムの絵というのは「え?これ、描いたの?」と驚かされるんだけど、たくさん見ると疲れて、飽きる。画家の「どうだ」が入っていて、腕自慢の連続に「はいはい、そうですか。すごいすごい」と辟易してくるのだ。
赤瀬川さんのカメラの絵は疲れない。自慢の代わりにユーモアがあるからだ。
自分が一番好きなものを、楽しんで描いているからだろう。とはいえ、本人から、1枚描き上げるとヘトヘトになるよ、と聞いたことがある。楽しみながらも、魂を削って描いたものなのだろう。
本には、こんな絵が246点も掲載されている。
並外れた観察力・描写力と根気、クラシックカメラに対する深い愛情の結実だ。
この本は、赤瀬川さんにしか描けない、後世に残る、世界一のカメラ画集だと思う。
生前に出版されなかったことが、残念でならない。
赤瀬川さんの画家としての、最後で最高の画業だ。
クラシックカメラにほとんど興味がないボクでも、思わず見入って、うーんと唸りながら、ページをいつまでもめくってしまう。
この机で原稿を書かねばならない時間が、どんどん過ぎていく。
でもその間、ボクの目は、赤瀬川さんに再会しているような、不思議なしあわせに浸っていた。
荒川の向こうへ出かけて鉛筆工場へ。赤瀬川さんに導かれたかナ
さて、今回の偶然は、途中めしのテーマが、荒川の向こうで鉛筆工場を見学してから、エチオピア料理を食べる、だったことだ。
そこから帰ってきて、すぐに赤瀬川さんのカメラ鉛筆画集が届いた。
偶然の鉛筆繋がりだ。
この企画を考えたのは編集者男だ。辣腕編集者は偶然をおびき寄せる。
で「鉛筆工場の見学」だが、その企画自体は楽しい響きを持っているけど、実はそんなに興味がなかった。今鉛筆を使わないこともあるけど、子供の頃に「絵本百科」という大判の児童向け百貨辞典で読んで知っていたからだ。
そしたら当日、仕事が押して、見学に遅刻してしまった。工場見学は、事前に予約して、決められた時間にいかねばならない。遅刻したら参加できないのだ。
場所は葛飾区四ツ木。
工場へ着いた時は、もう編集者男と編集者女は見学の最中だった。
北星鉛筆。ほとんど使ったことがないが、名前は知っている。
工場のビルは壁面に大きくカラフルな鉛筆のイラストが描いてあって、すぐわかった。楽しくなる建物だ。
でもボクは外で待ちぼうけ。仕事できたのに情けない。別の日に来ようか。いや、来なければダメだろう。大人として。
工場の入り口には大きな鉛筆が立っていて、そこに取り付けられた小さな鉛筆が見学受付や出荷事務所の方向を指している。
2本足で立ち上がった茶色い犬の像もあり、
「いらっしゃいませ ペコはとってもうれしいワン」
という札を紐でくわえて下げている。
さらに小さな庭には「鉛筆神社」というのがあった。鳥居も鉛筆型6角柱でできている。
隣には「我が身を削って人のため 鉛筆の道」というこれまた太い鉛筆型棒杭が立っている。この先端の芯部分が鉄の蓋で開閉でがき、中に短くなった鉛筆を供養するようになっている。
そう言えば昔、赤瀬川さんはちびた鉛筆ばかり書いていた時期があった。そんな絵のポスターを、20歳ごろずっと実家のボクの部屋の机の前に貼っていた。懐かしい。
けっして大きくはないが、いろいろ楽しい工場だ。
なんだか鉛筆が、あらためて愛おしくなってきた。
ボクの小学校の頃は、ユニとかモノとか、ちょっと高級鉛筆が発売された。いつも鉛筆でわら半紙(一番安いやや茶色い紙)に好きな絵を描いていたボクには、それらがすごく憧れだった。たまに買ってもらえると、嬉しくてたまらなかった。
また鉛筆で絵を描こうかな。
今なら赤瀬川さんの影響を受けないで描けそうな気がする。
そうして、しばらくして編集者男と編集者女は出てきた。
ボクは申し訳ない気持ちと、情けない気持ちで、どう対応していいか困って恐縮したが、2人はなんだか楽しそうだった。
鉛筆の製作過程を聞くと、ボクが50年前に読んだ通りだった。芯を並べて2枚の板で挟み、それを切り分けて6角形の持ちやすい形に削る。その絵まで覚えている。まだ変わっていないのか。
でもその時に出るおが屑を、北星鉛筆では、手にべとつかないねんどにしたり、絵の具にしたりしている。木製ねんどは乾燥すると木になり、切ったり削ったりが可能だそうだ。木製絵の具も乾くと木になる世界初の絵の具とのこと。ちょっと使ってみたい。
こうした木のリサイクルにも取り組んでいるそうだ。
初めての町。葛飾四ツ木。なんだか良さげな居酒屋があるッ
さて、遅刻した反省は、あっという間に忘れて、ボクは2人と四ツ木散歩に出た。
四つ木駅は京成押上線で、荒川を渡った最初の駅。降りたのは初めてだ。
ひとつ先が立石で、ここは友人や編集者と何度も居酒屋に飲みに来た。
今ではすっかり居酒屋マニアで有名な、もつ焼きの「宇ち多゛」。初めて行ったのは30年近く前か。まだ空いていた。安くておいしい独特のもつ焼きと、独特の注文ルールがある。面白い店があるものだなあ、と思った。もう10年ぐらい行ってない。
でも四ツ木のことはまったく知らない。
「とりあえず荒川でも見ますか」
と編集者男が言うままに、そっちへ向かうことにした。
すると太い通りに出たところに、「大衆酒場ゑびす」というのがあった。
まだ新しい5階建てのマンションの一階だ。
時間は4時過ぎだったが、もう暖簾が出ている。
長大な紺暖簾には、横書きにでかでかと「大衆割烹」と書いてあり「衆」と「割」の間に小さく「ゑびす」と縦書きに染め抜いてある。
もうこの堂々たる暖簾だけで、いい店の予感がビンビンにする。
いや、間違いなくいい店だろう。有名かもしれない。
昔からここにあって、一度店舗を取り壊して閉店して、最近同じ場所でマンションの中に入って再開したのではないか。
「入りますか」
と編集者男が言い、編集者女も
「この後に予約しているエチオピア料理まで、2時間近くあるから、入りましょう」
と言った。
だが2時間も飲んでたら酔ってしまう。というか、工場見学できなかったまま飲み屋に行くのも、気がひける。
と思っていたら、どこからともなく、中年で鼻の下にひげを生やして、おかっぱっぽい長髪に登山帽っぽいハットを被り、ショルダーバッグを下げ、スリムのジーンズに革靴、10年ぐらいこのファッションが固まったままのような男が現れ、さかんに店をスマホで店の外観を撮り始めた。
少し離れていた我々は目に入らないようだ。そしていそいそと店に入って行った。
間違いない。居酒屋マニアだろう。
彼の後に続いて入るのは、なんだかわかんないけど、少し嫌だ。
よかった。吹っ切れて荒川を目指す。
川に向かう道すがらも居酒屋がたくさんある。新しい建屋のところが多いが、最近開店したとは思えない雰囲気は、どこからくるのだろう。
川沿いの車道に出た。信号で渡って、土手に上がる。
スカイツリーが左前方に見え、京成線の鉄橋も見えた。
下は細い綾瀬川で、その向こうに大きな荒川があるようだ。
夕景が始まっていて、青空に雲が美しい。
橋を目指して歩く。
ジョギングしている人がいた。
学生服で自転車で急いでいる少年がいた。
セミアコースティックギターと小さなアンプを持って来て、1人でギターを弾いている若者がいた。譜面台も立てている。ジャズギターの練習をしているようだった。
波のないツルツルの綾瀬川に映る西の青空に、薄いオレンジ色が広がり始めている。そこに映る雲が美しい。
その向こうの荒川の土手上の道は、雑草に挟まれているようだ。
スカイツリーはすっかりシルエットになってきた。
土手の上を自転車でゆっくり走っていく、野球帽をかぶったおじさんのシルエットが絵のようだ。
橋のところまできた。
荒川が広い。ボクの一番よく知っている一級河川の多摩川とも、隅田川とも、全然景色が違う。どこが違う、とすぐに言えない。
広い川面は、大きな鏡のように、西の空と雲を映している。
いよいよ眩しい夕陽が沈むところだ。
グレーの雲もオレンジ色に色づき、太陽の近くは金色に輝いている。
ボクら3人は呆然とそれを見ていた。

編集者女が、
「夕陽が沈むところを見るのって、いつ以来だろ」
と呟いた。確かにこういう時間を、旅先以外で、東京都内で黙って過ごした記憶が出てこない。
橋をたくさんの人が行き来している。自転車の子供から、お年寄りまでいる。みんな家に帰るんだろう。
毎日、雨の日も風の日も、この大きな橋を渡る生活。
橋もまた、橋の向こうとこちらの途中、途中建造物だ。
夕陽が完全に沈むまで見届けて、ボクらはゆっくり道を引き返した。

ひっそり、堂々とした居酒屋。昨日、今日できた店じゃない
当然のように3人は「ゑびす」にやって来た。
店に近づくと、なんとさっきの居酒屋マニアさんが、ガラリと店から出てきた。30~40分たっていただろうか。
ちょっと赤い目をしている。
しかし、店から出てくるなり、その場に立ち止まって、バッグからムックのようなものを出し、その地図をにらんでいる。
次の居酒屋に行くのだろう。この店のチェックはすんだのか。なんだか確認飲みだ。ご苦労さまなことだ。
暖簾をくぐり、3人で店に入った。
店は長いカウンター席と座敷があった。店の中もまだ新しい。
その新しい壁に、酒と肴の短冊が、びっしりと貼り巡らされている。すごい数だ。やはり昨日今日にできた店ではない。
まだ空いていたので、カウンターに座ろうとすると、女店員さんに「あちらへお願いします」と、ビシッと言われ、座敷に案内された。でもそれはけっして嫌な感じではなかった。
そして、座敷の卓に着くと、店員さんが我々の靴をそれぞれビニール袋に入れて差し出し、
「わからなくなってしまうから、これでそちらに預かってくださいね」
と言った。
時々入り口でビニール袋を差し出して、靴はめいめい席に持っていけという店はある。ここもそうなんだろうが、ルールを知らない一見の客に、持ってきて言い添えてくれるのは親切だ。
瓶ビールをもらって、かつお刺身と菊の花のおひたし、そして古漬けを頼んだ。丼ものやご飯類も充実している。やっぱりいい店だ。
店はいつの間にか混んでいて、年配客も多く、ほとんどの客が近所の人のようだった。みんな楽しそう。それが一番だ。
エチオピア料理の大皿一気盛りに感嘆する
とはいえ、我々はここで終わるわけにはいかない。
駅向こうにある、エチオピア料理の店に移る。
駅からすぐの「エチオピア・レストラン&バー」。
入ると先客は誰もいなかった。
小さな店だ。

モニターでダンスミュージックのPVが流れているが、エチオピアのミュージシャンではなさそうだ。
エチオピアの人であろう女性店員が出てきたので、ビールを頼むと、イスラエルのビールが出てきた。

イスラエルのビールは、薄くて、泡もすぐ消えてしまうタイプだった。
メニューを見たけど、オニオンリングとか、鳥唐揚げとか、ミニ野菜春巻きと、全く日本の居酒屋メニューだ。それが1ページに1品ずつ写真付きで載っている。これはツマラナイな、と思っていたら、
「コースと聞いています」
と女店員が言ったので、それでいいです、と安心した。
女店員が厨房に入ってしまうと、カウンターの中に若い子が座っているのに気づいた。その子がリモコンを操作して、モニターを見ていて、時々一緒に歌っている。時々「コレおもしろい。これ大好き」とか、ボクらに言うともなく言い、でも時々こっちを見てニコニコする。
さて、コースは、すごく大きな大皿に全部のって出てきた。
こういう形態の「コース」は初めてだ。
チキンカレー、ビーフカレー、ハチノス、ひよこ豆、ほうれん草、あと、レンズ豆のサラダ。
これらがクレープのような柔らかくて薄い「インジェラ」というエチオピアのパンに囲まれている。
どれもおいしかった。みんなカレー風だけど、やはりインドカレーとは違う。それほど辛くない。
日本人の舌に合わせているのかわからないけど、エスニック感はそんなになかった。
そんなにスパイシーではない。よくいえばまろやか、でもガツンという香辛料はない。そこが物足りないといえば物足りない。
とはいえ、どんな形になっても、カレーは強い。
ボクはチキンカレーがおいしかった。ライスでも食べてみたい。
レンズ豆のサラダが、しゃきっとして、コースの中でいい働きをしている。
ハチノスがおもしろい。
日本人的な、ご飯とおかず、という食事ではない。
でもみんなでこれを食べるのは楽しそうだ。日本で言えば、家庭でやる五目ちらし寿司に似ているのかもしれない。エチオピア式五目ちらし寿司、と思って食べたらまた違うかもしれない、と今書いていて思った。

大皿を持ってきた時、初めて厨房からご主人が現れた。日本語もうまく、物腰がやわらかい。
そしたらカウンターの中から女の子が出てきた。お父さんが大好きなようで、太い腕にぶら下がったりしている。
カウンターの中にいる時、中高学生ぐらいかと思っていたら、もっとずっと小さくて、聞いたらなんと5歳だった。なんだか恥ずかしくなった。

3人家族のようだ。この辺りにはエチオピアの人が多く住んでいるそうで、週末は店に集まるそうだ。
でもこの日の客は、最後までボクらだけだった。
食事の後、コーヒーが出た。コーヒーは、素焼きのポットで出され、入れる時は乳香というお香を焚く。そしてハーブを浮かべて飲むのだった。
お香の香りは、気分を変える。そうだ、エチオピア料理だった、と酔いかけた頭が思い出す。
ここが一番異国情緒あり、今日の取材の締めくくりとして、すごくよかった。
ボクはエチオピアのことを全然知らないないんだなぁ、とコーヒーをすすりながら思った。

紹介したお店
営業時間:ランチ 11時~14時/ディナー 18時~23時(ビール・ワイン・カクテル ハッピーアワー18時~19時オール400円)
定休日:月曜日(日曜日営業)
※掲載された情報は、取材時点のものであり、変更されている可能性があります。
著者プロフィール

文・写真・イラスト:久住昌之
漫画家・音楽家。
1958年東京都三鷹市出身。'81年、泉晴紀とのコンビ「泉昌之」として漫画誌『ガロ』デビュー。以後、旺盛な漫画執筆・原作、デザイナー、ミュージシャンとしての活動を続ける。主な作品に「かっこいいスキヤキ」(泉昌之名義)、「タキモトの世界」、「孤独のグルメ」(原作/画・谷口ジロー)「花のズボラ飯」他、著書多数。最新刊は『ニッポン線路つたい歩き』。