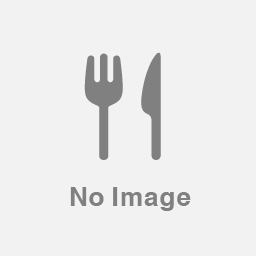高円寺にビリヤニをメインにした新店が誕生!
ガチなカレー好きの割合が日本有数で高い街、そしてどことなくインドの気配や空気を感じさせてくれる街、なんて私が勝手に思っている高円寺。そこの高架下に2020年3月、「エリックサウス 高円寺カレー&ビリヤニセンター」がオープンした。
エリックサウスといえば、南インドの本格カレーやミールス(定食)が食べられる人気の飲食店グループ。各店でメニューの一つとしてビリヤニを用意しているが、この新店舗ではカレーと同格の扱いでビリヤニを看板に掲げているのだ。
 駅の改札からすぐ、高架の南側にあります。
駅の改札からすぐ、高架の南側にあります。
 昼間のチョイ飲みにも良さそうな店。
昼間のチョイ飲みにも良さそうな店。
……ところでビリヤニってなんだっけ?
ということで話を伺ったのは、エリックサウスのメニュー開発を担当しているイナダシュンスケさん。外食産業に関する新書やカレーレシピ本を執筆し、当サイトでもライターとして活躍する話題の人である。

――すみません、ビリヤニとはどんな料理ですか。
イナダ:「ビリヤニは西アジアで生まれて、ムスリム(イスラム教)の人たちがインドを支配した歴史の中で、贅沢な宮廷料理として入ってきました。
バスマティというインドの香り米を、肉を中心とした具、スパイスと一緒に炊き込んだもの。インド風スパイシーパエリアなんていう説明をしています。
その起源は諸説ありますが、肉を煮るときにエキスが出るので、それを無駄にしないよう米に吸わせたのが始まりともいわれています。これは眉唾の話ですが、肉は贅沢品だったので堂々と調理するのは都合が悪い。そこで米で隠して肉で煮たのが始まりだという説もあったりします」
 左が日本米のあきたこまち、右がバスマティ ※自宅にて撮影
左が日本米のあきたこまち、右がバスマティ ※自宅にて撮影
「日本人がイメージする炊き込みご飯と違うのは、米を美味しく炊くために、具を入れてご飯に味わいを足す料理ではないこと。
ビリヤニは米料理ではなく肉料理、肉が主役です。調理前だとバスマティ100gに対して肉が150~200gのように、肉の方が多い。ただしバスマティは炊くことで日本米以上に水を吸って増える。100gだった米は300gくらいになり、逆に肉は加熱で縮むので200gは150gとなり、割合が逆転します。結果として炊き込みご飯のようになりますが、原材料をみればやっぱり肉料理なのです」
――ビリヤニの値段がカレーに比べて、ちょっと高めになっている理由がわかりました。妙に高いカレーチャーハンだなーと思っていた時期もありましたが納得です。
 左がバスマティ100g、右が牛肉200g ※自宅にて撮影
左がバスマティ100g、右が牛肉200g ※自宅にて撮影
 上のバスマティと牛肉でビリヤニっぽいものを作ってみたら、お米の量が増えて驚いた。 ※自宅にて撮影
上のバスマティと牛肉でビリヤニっぽいものを作ってみたら、お米の量が増えて驚いた。 ※自宅にて撮影
――米料理ではなくて肉料理ということですが、その具体的な作り方を教えてください。
「インドは広いので、ビリヤニといってもいろんな作り方があります。まず生米に具材やスパイスをたっぷり混ぜて一緒に炊く、日本の炊き込みご飯に近いもの。これを当店では『オリジナル』と呼んでいます。
もう一つが、先に生米をスパイスがたっぷり入った熱湯で香りをつけながら硬めに茹でて(7割くらい火を通す)、お肉やスパイスが混ざったマサラ(濃いカレーのようなもの)と重ねて、密封して蒸し焼きにする調理法。こちらは『ハイデラバーディクラシック』と呼んでいて、1人前ずつキャセロールで提供します。密閉して加熱すると、マサラのスパイシーなスープが蒸発して、それを米が受け止めて炊きあがるというメカニズムです」
 左が炊き込み式の『オリジナル』で「南インド・タミル地方のスタイルをアレンジした、日本人好みの当店オリジナルビリヤニ」と説明されている。右は固茹での米とマサラを重ねて蒸す『ハイデラバーディクラシック』、「ビリヤニの聖地ハイデラバードの古典的な製法を用い、1人前ずつ炊き上げる鮮烈な香りをお楽しみください」とのこと。
左が炊き込み式の『オリジナル』で「南インド・タミル地方のスタイルをアレンジした、日本人好みの当店オリジナルビリヤニ」と説明されている。右は固茹での米とマサラを重ねて蒸す『ハイデラバーディクラシック』、「ビリヤニの聖地ハイデラバードの古典的な製法を用い、1人前ずつ炊き上げる鮮烈な香りをお楽しみください」とのこと。
 「食べやすい←→マニアック」というベクトルがあるビリヤニマップ。食べやすいを「知っている味」と置き換えるとわかりやすいかも。
「食べやすい←→マニアック」というベクトルがあるビリヤニマップ。食べやすいを「知っている味」と置き換えるとわかりやすいかも。
 もちろんカレープレートやミールスもあります。
もちろんカレープレートやミールスもあります。
――炊き込み式と重ね蒸し式があるんですね。後者のハイデラバード方式が本格的ということですか?
「ビリヤニの本場はインドのハイデラバードですが、この重ね蒸しがハイデラバード特有という訳ではなく、さらにいえばハイデラバードが全部がこうという訳でもない。ハイデラバードで店の人に見せてもらったら、炊き込み式だったこともあります。
ビリヤニの歴史を語る上で、ムガル帝国(インドを支配したトルコ系イスラム王朝)の物語だったり、宮廷料理としての伝統だったりが出てきますが、実は近代になってから作られたストーリーかもしれない。ハイデラバードでイラン人がビリヤニ屋をやるにあたって、都合の良いビリヤニ史を作り上げて宣伝し、それが史実として広まっているという話もあります。
だから『伝統的なビリヤニはこうである』という説はいろいろありますが、私を含めてどれも信憑性100%ではないんです。でもそれらの伝承の中に、きっと何らかの真実が隠されているとは思います」
――客観的に正しい『元祖』とか『発祥』は、もはや誰にもわからないと。
「そもそもインドには名もなき米料理がたくさんあった。これは日本でも中国でも、世界中にありますよね。インドでは最近(といっても100年前とか?)になってからビリヤニという料理がステータスを持ったことによって、郷土の米料理がこぞってビリヤニを名乗り出し『おらが町のビリヤニ』が各地に生まれたというのが、インド料理に詳しい小林真樹さんの説です。
インドは広くて複雑な国です。土地ごとの差、さらには民族や宗教といったレイヤーがあるので、単純に『ビリヤニとはこうだ!』と言い切れる料理ではない。ちょっと話が盛られているかもと思いつつ、そのストーリーや味の広がりを楽しんでください」
――これはとにかく食べてみないとわからないやつですね。わかりました、この店にある全6種類のビリヤニをください!
※今回はビリヤニをたくさん食べるため4人で来て、撮影後に取り分けてから試食しました。
 前菜にいただいた『パパダチ・キスムール~パパドと香味野菜のタマリンドサラダ~(香ばしい豆せんべいのパパドを使ったおつまみにぴったりのゴアのストリートフード)』。もともとは干し魚や干しエビで作るゴア地方の家庭常備菜で、それがベジタリアン料理として進化したもの。甘くて酸っぱくて辛くて美味しく、そこにパパドや生野菜の歯ごたえが加わるにぎやかな味。
前菜にいただいた『パパダチ・キスムール~パパドと香味野菜のタマリンドサラダ~(香ばしい豆せんべいのパパドを使ったおつまみにぴったりのゴアのストリートフード)』。もともとは干し魚や干しエビで作るゴア地方の家庭常備菜で、それがベジタリアン料理として進化したもの。甘くて酸っぱくて辛くて美味しく、そこにパパドや生野菜の歯ごたえが加わるにぎやかな味。
 『前菜3種の盛り合わせ』は、色と味の組みあわせが華やかだ。『スンダルサラダ(ひよこ豆とキューブ野菜)』はココナツとレモンで風味付けした豆と野菜のサラダ、『キャロットラペ3種柑橘とローストクミン風味 』はグレープフルーツ、レモン、オレンジで風味付けしたフルーティーな人参サラダ、『アンドラ風チキンピックル』は、マスタードを効かせたスパイスオイルとビネガーでマリネした南インド風冷製チキン。こういうのをつまみながら酒を飲みつつ、ビリヤニが炊けるのを待つ訳ですよ。
『前菜3種の盛り合わせ』は、色と味の組みあわせが華やかだ。『スンダルサラダ(ひよこ豆とキューブ野菜)』はココナツとレモンで風味付けした豆と野菜のサラダ、『キャロットラペ3種柑橘とローストクミン風味 』はグレープフルーツ、レモン、オレンジで風味付けしたフルーティーな人参サラダ、『アンドラ風チキンピックル』は、マスタードを効かせたスパイスオイルとビネガーでマリネした南インド風冷製チキン。こういうのをつまみながら酒を飲みつつ、ビリヤニが炊けるのを待つ訳ですよ。
 浮かれて『ハイデラバーディバーベキュー』というチキン、ラム、ビーフの盛り合わせも頼んだ。肉をスパイス、ヨーグルト、グリーンチリでマリネしたスパイシーな串焼きで、ごちそう感がすごい。小皿に用意されたカレーリーフが香る魔法の粉(スリランカ料理のポルサンボルをシンガポールチャイニーズのシェフが魔改造したものをイナダさんがさらに魔改造)がうまいんですよ。
浮かれて『ハイデラバーディバーベキュー』というチキン、ラム、ビーフの盛り合わせも頼んだ。肉をスパイス、ヨーグルト、グリーンチリでマリネしたスパイシーな串焼きで、ごちそう感がすごい。小皿に用意されたカレーリーフが香る魔法の粉(スリランカ料理のポルサンボルをシンガポールチャイニーズのシェフが魔改造したものをイナダさんがさらに魔改造)がうまいんですよ。
炊き込み方式のエリックチキンビリヤニとマトンキーマビリヤニ
最初に登場したのは『ツインビリヤニ』。これは炊き込み式ビリヤニの『エリックチキンビリヤニ』と『マトンキーマビリヤニ』の両方を1皿に盛った欲張りなハーフ&ハーフだ。
重ね蒸しの『ハイデラバードクラシック』が1人前ずつ炊くスタイルのため20~30分待つことになるのに対して、まとめて炊く『オリジナル』は、ほぼ待ち時間なく提供してもらえる。
 左がエリックチキンビリヤニ、右がマトンキーマビリヤニ。
左がエリックチキンビリヤニ、右がマトンキーマビリヤニ。
写真左側の黄色い『エリックチキンビリヤニ』は、メニューに「バスマティライスの一粒一粒に、チキンの旨味と馴染み深いスパイスの香りが染み込んでいます ビリヤニが初めての方にもおすすめです」と書かれている。イナダさん曰く、抽象的に言うなら日本に馴染みやすい味、いわゆるカレー味とのこと。
さっそく食べてみると、すごくおいしいパラパラのカレー味炊き込みご飯というのが正直な感想だ。多くの日本人にとってしっくりくるカレー味で、鶏肉の旨味とスパイス感が米に浸透している。まさに説明文通りの味。
この味こそが、まだ日本でビリヤニという料理名を知る人が少なかった時代に、エリックサウスで初めて出したオリジナルだ。
 インドではビリヤニといえばコーラらしいので、スパイスウォッカ(シナモン、カルダモン、クローブなどを漬けたウォッカ)のコーラ割りを注文。コーラの持つスパイス感をストロングにした感じで大変おいしい。
インドではビリヤニといえばコーラらしいので、スパイスウォッカ(シナモン、カルダモン、クローブなどを漬けたウォッカ)のコーラ割りを注文。コーラの持つスパイス感をストロングにした感じで大変おいしい。
続いては写真右側、薄茶色の『マトンキーマビリヤニ』。こちらの説明は「レモンリーフやミントなどのハーブとホールスパイスの香り、後を引く芳醇なフレイヴァーとバスマティのふわパラ感をより楽しめるビリヤニです」だ。
「インドの北東部、ベンガル地方のビリヤニです。レモンリーフやミントを使うことで、いわゆるカレー味ではない味になっています。『オリジナル』は2種盛りにしたかったので、こっちのマトンキーマはエリックチキンとまったく違う、被らない味にしました。ビリヤニを食べ慣れた手練れこそが、おもしろがって食べてくれる味かもしれません」
チキンビリヤニとどう違うんだろうと食べてみると、私の知っている範囲ではタイ料理に近い風味で、ここまで違う味なのかと驚いた。バイマックルー(コブミカンの葉)の香りが効いていて、タイ風チャーハンといわれたらそうなんだと思ってしまうだろう。口の中ですごく軽く、確かにふわパラ感が楽しめる。スパイスの奥深さを思い知らされる2つの味が、1皿で気軽に食べられる喜び。
これらのビリヤニをさらに楽しませてくれるのが、横に添えられたライタ(刻み野菜入り塩ヨーグルト)とナワブチキングレイヴィの存在だ。
 ビリヤニにはライタとグレイヴィが付いてくる。
ビリヤニにはライタとグレイヴィが付いてくる。
「ビリヤニにライタを添えるのはインド全土ではないですが、ハイデラバードでは定番。ライタなしではありえないくらい合います。途中でビリヤニに掛けて、味を変えてみてください。
ナワブチキンはハイデラバード名物のカレーです。ただこういったカレーソース的なものをビリヤニと一緒に食べるのはインドだと少数派。ちょっと邪道だけど美味しいよねっていう感覚でつけています」
チキンビリヤニにチキンカレー的なソースを掛けちゃうのは、エビチャーハンにエビチリを掛けるみたいな、美味しいものに美味しいものを足したらすごく美味しいよね!という、個人的には大好きな計算方法だ。カレー屋が出すビリヤニなのだから、できればカレーをつけてほしいという要望があるのだろう。
この1皿だけでも十分楽しめたのだが、ビリヤニセンターの本気度はここから一気に加速していく。
これぞビリヤニの本流、骨付きマトンビリヤニ
ここからは怒涛のハイデラバーディクラシックの4連発である。ちなみにここから先はメニューに料理の写真がないので、どんなものが出てくるのか全く不明。ここで知りたくない人は、ページを一旦閉じて店に直行するのもいいだろう。
1発目はビリヤニのド定番、ド真ん中、これぞオーセンティックだという『骨付きマトンビリヤニ』。テーブルに届いたのは小さなココットだ。
 予備知識がまったくないと、「あれ誰かスープグラタンかポトフでも頼んだかな?」と思うかもしれないが、これが1人前ずつ炊くエリックサウス独特のビリヤニ容器。おそらくインドでこういう提供方法をしている店はほとんどないのでは。
予備知識がまったくないと、「あれ誰かスープグラタンかポトフでも頼んだかな?」と思うかもしれないが、これが1人前ずつ炊くエリックサウス独特のビリヤニ容器。おそらくインドでこういう提供方法をしている店はほとんどないのでは。
料理の説明は「スパイス・ハーブ・グリーンチリをふんだんに使用、目の覚めるような香りと辛さが羊肉の旨味を最大限に引き出す当店イチオシのビリヤニ」。
米料理ではなく肉料理だという本格派のビリヤニ、さてどんな姿をしているのか!
フタをオープン~!
 日の丸弁当を彷彿とさせる衝撃のヴィジュアル。スターアニスを中央に置けばインドの国旗っぽくなるかも。
日の丸弁当を彷彿とさせる衝撃のヴィジュアル。スターアニスを中央に置けばインドの国旗っぽくなるかも。
わー、米と枯れ葉みたいなスパイスしかない!冬の公園みたいな寂しさはどういうことだ!米より多いという肉はどこへいった~!と焦りまくる。匂いはすごくいいんだけど!
しかしスコップケーキのように縦方向に掘っていくと、中央に厚い肉の層を発掘!お肉だ~!
 肉の隠し方が沖縄の宮古島で食べられている宮古そばっぽい。ビリヤニが贅沢品であった肉を隠す料理という説があるのもわかるな。
肉の隠し方が沖縄の宮古島で食べられている宮古そばっぽい。ビリヤニが贅沢品であった肉を隠す料理という説があるのもわかるな。
「硬めにスパイスと茹でたバスマティで羊のマサラを挟み、蒸し焼きにしています。下段がしっかりと味の染みた米、中段にはスパイスを効かせた肉、そして上段が肉の蒸気で蒸された米。
これをあえてまだらを残しつつ食べるのがオススメ。完全に混ぜるよりもリズムが出て美味しいんです。インドだと人によっては徹底的に混ぜますが」
 まだらな感じがうまいんですよ。ハーブの感じが強く、ドライミントの爽やかな香りが羊と合う。
まだらな感じがうまいんですよ。ハーブの感じが強く、ドライミントの爽やかな香りが羊と合う。
肉の周りで汁を吸った米が躍っている。なるほど、これはさっき食べた肉の串焼きの延長線上にある料理。肉を串に刺して焼くか、米と煮るかの違いだ。ビリヤニは肉料理であるというのがよくわかる。
これだけ肉のエキスを吸わせてあるのにサラサラなのは、バスマティならではなのだろう。メニュー表に写真を載せても、まったくピンとこない料理だろうな。
これを食べるとビリヤニが単純にカレー的な食べ物という訳ではないことがよくわかる。たくさんのスパイスが使われているのだが、そのベクトルはいわゆるカレーとまったく違い、さっき食べたマトンキーマとも全然違う。ビリヤニ、おもしろいなー。
インドではきっと食べられない味、鯖ビリヤニ
ハイデラバードの2発目は、本場だと食べられないであろう『鯖ビリヤニ』だ。説明は「個性的なスパイス&ガーリックの風味と爽やかなレモンの香りが、脂の乗ったサバの力強い味わいを引き立てます」と書かれている。この文章だけ読むと、ビリヤニの解説だとは絶対に思えないだろう。
 フタを開けるとレモンとディルだけ。ビリヤニ海峡冬景色か。これが遠足のお弁当だったら泣く。
フタを開けるとレモンとディルだけ。ビリヤニ海峡冬景色か。これが遠足のお弁当だったら泣く。
「上から見ると米とレモンとディルしかありませんが、サバが真ん中にドーンと入っています。フィッシュビリヤニは、インドだと無くはない、という感じで非常にマイナーな存在。海から遠いハイデラバードだったら川魚を使うでしょうね。
製法としてはマトンビリヤニと一緒。生のサバでマサラを作って、バスマティで挟んでいます。ヨーロッパだとサバとジャガイモをよく合わせるし、ビリヤニにジャガイモを入れることが多いので、具にジャガイモを選びました。これは予想以上にファンが多いビリヤニです」
 しっかりと脂の乗ったサバが肉以上に主張をする。そしてジャガイモがうまい。
しっかりと脂の乗ったサバが肉以上に主張をする。そしてジャガイモがうまい。
日本だったら魚の選択肢はいくらでもあるのに、あえて青魚のサバである。食べてみると肉系とはやっぱり印象が全然違った。レモン風味でさっぱりしつつも、脂の乗ったサバがしっかりと主張していて、これを好きな人が多いというのもわかる気がする。
「ハイデラバーディクラシックのビリヤニは、グレイヴィがナワブチキンとサランから選べます。ハイデラバードではビリヤニのお供としてライタと並んで定番のミルチカサランという、青唐辛子とナッツペーストのカレーがあって、それをそのまま日本で出すとドン引きされそうなので、カレー寄りにしたオリジナルグレイヴィがサランです」
ベジ(肉類不使用)であるサランはナワブチキンに比べてカレー感が抑えめなので、そこまで全体を支配せずに味の変化を与えてくれる。鯖ビリヤニのような独特の個性を消したくなければ、こちらのグレイヴィがベターかもしれない。
それにしてもイナダさんのメニュー開発、自由だな。サバって。
肉を使わないメニューもある!ベジタブル&パニールビリヤニ
先ほどからビリヤニは肉料理だという説明をみっちり受けてきたが、ここにきて肉が入っていないビリヤニ、『ベジタブル&パニールビリヤニ』が登場だ。説明によると「コクのあるスパイスを使い、ごろごろ野菜とインド式カッテージチーズのパニールで、肉にも負けない食べ応えです」とある。
ベジのビリヤニってどういうことだ。
 上に乗っている具は、プチトマト、ナッツ、レーズン。なかなかファンシーな見た目である。
上に乗っている具は、プチトマト、ナッツ、レーズン。なかなかファンシーな見た目である。
「ベジビリヤニはインドにもあります。インドは一定数以上のベジタリアンがいて、しかも上層階級に多い。そこで贅沢な宮廷料理であるビリヤニを食べられるようにアレンジする必要があって生まれたのではと考えられます。
ただ野菜を米と調理する料理はビリヤニが流行るよりも前からインド全土にあった訳ですね。名もなき郷土料理に対して、これはベジビリヤニだと名前をつけて、お金のとれるもてなし料理にしたのかもしれません」
 季節の野菜がたっぷり。
季節の野菜がたっぷり。
基本的な作り方は一緒で、こちらも米、具、米の三層構造。具は季節の野菜とチーズだけだが、食事としての物足りなさはない。味がとても華やかで、寂しい感じがまったくしないのだ。これもスパイスの神秘だろうか。
合わせるグレイヴィはベジのビリヤニなので、同じくベジのサランが正解だろうけど、個人的にはナワブチキンをドサッと掛けたい。やっぱり肉っ気が欲しくなる。
生肉と米を蒸し焼きにして作る宮廷料理、ロイヤルカッチビリヤニ
最後に登場するビリヤニは、その名も『ロイヤルカッチビリヤニ』。「スパイスとヨーグルトに漬け込んだビーフとチキンの2種類の肉を生から米に炊き込む、ハイデラバードの古典的な宮廷料理を再現しました」だそうですよ。
さすがはこの店で一番高いビリヤニ、そしてロイヤルを名乗るだけあって、なんと耐熱ガラスの器で登場だ。これぞビリヤニ界のシンデレラ!
 中央に乗せられたフライドオニオンの香りがすごい。
中央に乗せられたフライドオニオンの香りがすごい。
「カッチビリヤニは、生肉をスパイスやヨーグルトとマリネして、米と蒸し焼きにしたものです。これは下の層が肉で、上が米の2層。宮廷料理では贅沢を演出するために複数の肉を使うことが多かったので、ビーフとチキンを組み合わせています。これにはベジのグレイヴィがお勧めで、ライタがとっても合うんです!」
 写真だとわかりにくいけれど、下が具で上が米の2層構造。
写真だとわかりにくいけれど、下が具で上が米の2層構造。
そろそろビリヤニのレパートリーも尽きただろうと思ったら、これまでと違う製法のパターンが出てきた。食べてみるとスパイス感が予想外にまろやかで驚く。あくまで肉の旨味が前で、スパイスの刺激が後ろにいるのだ。確かにチキンのグレイヴィを掛けると蛇足感があるのかも。
肉をたっぷり使いつつも、さすがは宮廷料理と思わせてくれる上品さ。いわゆるカレー感が一番薄いビリヤニかも。こういう方向性でマニアックに攻めてくるとは。
多種多様なビリヤニ、しっかり堪能させていただきました!
なぜ高円寺にビリヤニセンターをオープンしたのか
こうしてお腹がいっぱいになったところで、せっかくの機会なのでイナダさんにもう少し雑談っぽい話もしてもらった。
――どうしてここまでビリヤニに力を入れた新店舗を、高円寺にオープンしたんですか。
「一昔前だったら考えられませんよね。ビリヤニをメインにしたお店をやりたいっていうのは数年前から構想はしていて、その間にいろんなスタイルを考えていました。7~8年前に考えたのが『ビリ二郎』。ラーメン二郎のビリヤニ版をやったらおもしれ~な~って。大釜でジャンジャンビリヤニを作って、肉増し!米大盛り!って出そうかなと思ったのですが、店側の人間が1週間くらいで飽きそうだなって。出オチみたいなもんなんで、やっても期間限定のイベントだろうと」
――ジロリアンならぬビリジアンが生まれていたかもしれない。
「ビリヤニと並行してカレーも出す形ならできそうだなと思いつつ、そうはいっていもビリヤニ中心なんていう業態が成り立つはずはない。考えを煮詰めていきつつも封印していたんですが、ここ2~3年でビリヤニの認知度が10倍、100倍に上がった。提供する店もどんどん増えている。これは思ったよりもハイスピードで世の中にビリヤニが浸透しだしているぞ、本当にやれちゃうなと思ったときに、ここの物件を紹介してもらったんです。カレー屋の多い高円寺で探したわけではなく、物件が先でした」
 本当は純粋なビリヤニ専門店にして、期間限定ビリヤニとかをフルスイングでやりたいのかもしれない。
本当は純粋なビリヤニ専門店にして、期間限定ビリヤニとかをフルスイングでやりたいのかもしれない。
「ここで店をやるとなると、ターミナル駅でも商業施設でもないので、たまたま前を通る人だけを相手にするのではなく、遠くからでもお客さんが目指してくれる店にしたい。わざわざ来てくれるにはどうしたらいいだろうと考えたときに、ビリヤニ専門という強いインパクトのあるコンテンツがあるといいよね!っていうのを言い訳にしてオープンしました。ビリヤニをやりたかったのを正当化して」
――話の後半に本音が漏れていますよ。でもあくまで『カレー&ビリヤニセンター』なんですね。
「カレーとビリヤニを両立させたのは、冷静に商売を考えて。ランチとかはふらっと食べにくるお客さんも多いので、ハードルが低いものもちゃんと一通り揃えようと。エリックサウスを知っている人ならミールスやカレーはないの?ってなりますし。ランチでカレー(ミールス)とビリヤニの割合は6:4くらいです」
 何を食べようか迷ったら、カレーとビリヤニと串焼きのセットという贅沢なプレートもある。このプレートも選択肢が豊富なので、結局迷うことにはなるのだが。
何を食べようか迷ったら、カレーとビリヤニと串焼きのセットという贅沢なプレートもある。このプレートも選択肢が豊富なので、結局迷うことにはなるのだが。
今回は4人で5皿6種のビリヤニ、さらに前菜に串焼きという豪遊をした。ビリヤニの見た目は全部似ているけれど、食べてみるとバラエティに富んだ味わいだったので、口が飽きるということはまったくなかった。これは貴重な経験だ。
このように数種類を少しずつ食べ比べるというスタイルはもちろん楽しいのだが、次は1人前をしっかり食べきるというのもやっておきたい。同じ味をモリモリと一心不乱に食べ続けることで、気が付くビリヤニの良さもあるはずだ。それが本来の食べ方だしね。
となると問題は、今度何を頼むかだ。メニューを前に30分くらい迷う自信がある。一通り食べてみたからこそわかるのだが、みんな違ってみんなうまい。ビリヤニらしいビリヤニで王道を歩むのもいいし、マトンキーマやサバのように中心軸から外れた味覚の辺境を旅する喜びもある。いやでもミールスだって食べたい。って今から迷ってどうするんだ。
 食べきれなかった場合は、持ち帰り用の容器がありますよ。
食べきれなかった場合は、持ち帰り用の容器がありますよ。
ビリヤニは単一の料理名というよりは、もはや『概念』なのかもしれない。日本の料理だったら、寿司、鍋、ラーメン、駅弁あたりの幅広さが近いだろうか。
もしかしたらの話だが、100年前の天才商売人によるブランディング戦略が、ここまでビリヤニの種類を増やした要因だとしたら最高だ。とにかくビリヤニはどれも美味しかった。
紹介したお店